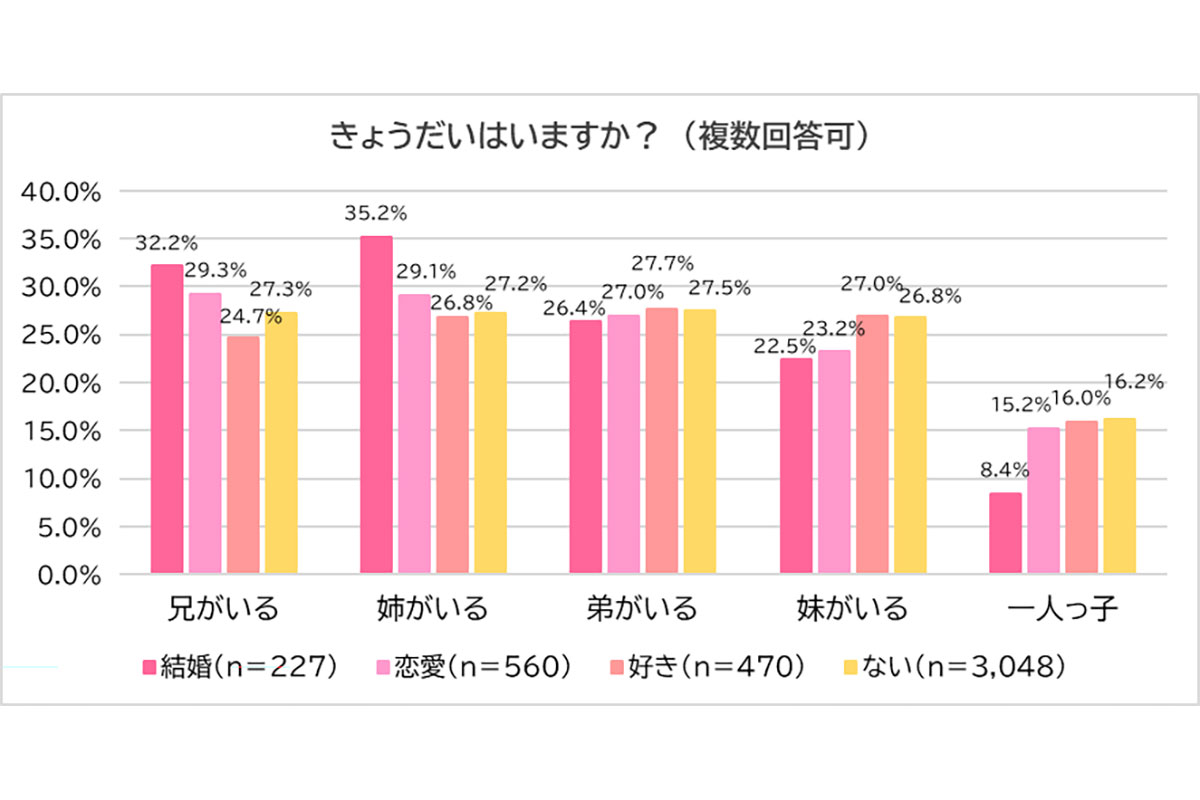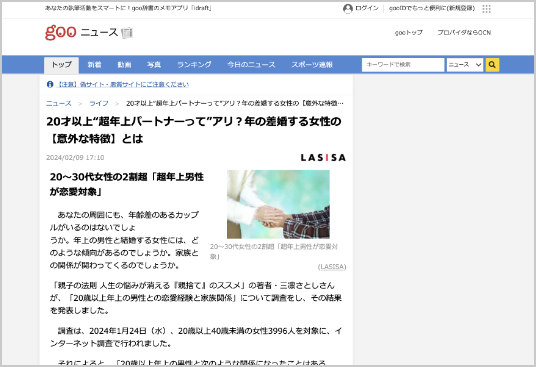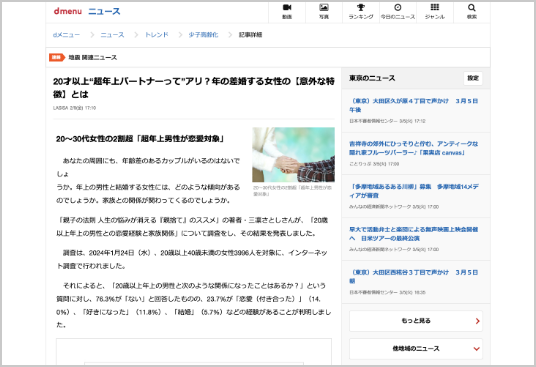資産形成ゴールドオンライン他、調査が掲載:2024年6月1日掲載
50代ひとり娘「もう私を頼らないで」と言い残し、実家をあとに…年金15万円・要介護の80代母、涙ながらに語った後悔
母と折り合いが悪い「ひとり娘」…母の介護は義務?
――母の面倒は私がみるべきでしょうか?
50代女性の投稿。母は80歳で、女性はひとりっ子。母とは折り合いが悪く、できるだけ距離を置いて生きてきました。
「自分は放っておかれた存在だった」と女性。専業主婦だった母はいつでも自分優先で、女性が子どもの頃は、とにかく趣味(音楽)にはまり、毎日のように練習で家をあけてばかりだったといいます。さらに、趣味を通じて知り合った友人とは、ことあるごとに食事にいき、しょっちゅう泊りがけの旅行にも。
一方で、女性が「習い事をしたい」といってもNG。なぜなら、自分に費やすお金が減るから。受験生のときには「塾に通いたい」といってもNG。それも、自分に費やすお金が減るからでした。
――とにかく私のことには無関心。いま思えば、ネグレクトだったと思う 参観日には来るはずもなく、運動会や学芸会などの行事に欠席することも。当時、父は単身赴任をしていて家におらず、また「仕事で忙しいお父さんの邪魔をしてはいけない」と自ら電話をすることは禁止だったので、女性がこのような状況にあったことを知るはずもありませんし、「そもそも父親に期待すらしていなかった」と女性。
とにかく、自分を差し置いて、我が子にお金をかけることを極端に嫌った母。高校までは進学できたものの、大学進学の際は猛反対。さすがに父が助け船を出してくれましたが、学費以外は出す気はなし。ただ母から離れたい一心で、家からは通うことのできない大学に進学し、生活費はすべて自分でどうにかしたといいます。
そんな母も80歳。昨年、父が亡くなると、頻繁に連絡が来るようになったといいます。
――母は要介護認定を受けていて、病院に付き添ってほしいとか、色々言ってくるんですが……いまさら、どの面を下げて頼んでいるんだか、という話ですよ。私はもう関わりたくないんです。
母との関わりを絶ちたいひとり娘だったが…
――いまでいうと、毒親、というやつでしょうか
と女性。「毒親」に明確な定義はありませんが、一般的には子どもを支配したり、傷つけたりして子どもにとって「毒」になる親のこと。その範囲は広く、子どもに愛情を注がず罵倒したり、無視したりというのもヒドイ毒親とされています。
合同会社serendipityが20歳以上60歳未満の男女に対して行った『親子関係についての調査』によると、「親と円滑なコミュニケーションが取れているか」の問いに対して、「いいえ」は男性が14.7%、女性が22.1%。また「親が毒親だったと感じることはあるか」の問いに対しては、「よくある」が男性25.5%、女性33.1%、「たまにある」が男性36.3%、女性32.8%と、双方合わせると、親が毒親だったと感じている人は実に6割に及びます。またその傾向は、男性よりも女性にほうが若干多いといいます。
「父が亡くなり、急に将来が不安になったことも、頻繁に連絡を寄こすようになった一因」と女性。ただ母は月に15万円程度の年金があり、父の遺産も十分。それらのお金で老人ホームに入ればいいだけ。 そう考えていたとき、母からの電話。なんでも湯を沸かそうとしたら大やけどをしたとのこと。これには女性も飛んで実家に帰ったとか。しかし、実家につくなり、それは母親の虚言であることが分かります。
――嘘でもつかないと、家に来てくれないと思って 母親は悪びれた様子もなく女性にいいます。怒る気力もなく、すぐに実家をあとにしようとする女性。
――もう私には頼らないで。施設にでも入って生きていって ぴしゃりを扉を閉めて家路につきます。しかし心のもやもやは晴れず、冒頭の投稿をしたという顛末。 厚生労働省『令和4年国民生活基礎調査』によると、「要介護者」からみて「主な介護者」で最多は「配偶者」で22.9%。続いて「子」が16.2%。「事業者」は15.7%で6~7人に1人という割合。家族ではなく。第三者に親の介護をお願いするのもひとつの選択肢です。 女性の投稿に対し、多くが「それはヒドイ!」「親子関係を切っても問題なし」など肯定的意見が目立ちました。
「もう、本当に関わらない」と心に決めたときに、母からの電話。「これが最後」という気持ちで出てみると、明らかに母が泣いているのが分かりました。 ――ごめんね、悪い母親で、本当にごめんね 何度も謝る母に言葉をなくす女性。「あの母が泣いて謝るなんて……」、衝撃的でした。それでも「泣いて許されるものではない」と女性が突き放しても、謝罪を繰り返す母。後日、再び実家に訪れた際も、母は泣いて謝るばかり。
「本当に面倒くさい」「こんな自分が嫌い」といいつつ、母に手を貸しているといいます。 ちなみに民法877条第1項によると、直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があると定められています。親の介護義務は、親の兄弟姉妹、子ども、孫にあります。親子関係が不仲であっても扶養義務を負う必要があるのです。
[参考資料]
合同会社serendipity『親子関係についての調査』
厚生労働省『令和4年国民生活基礎調査』
その他のメディアにも転載されました!
Yahoo!ニュース

Rakuten Infoseek News

livedoor News
Girls Channnel
その他、gooニュース、dmenu ニュースなど